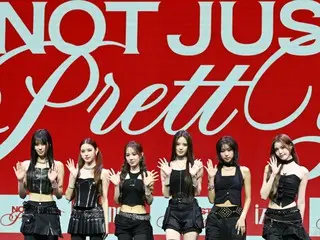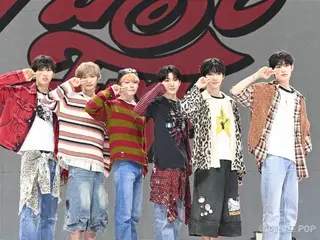2015年3月30日に厚生労働省はマタニティハラスメントの問題を受けて、妊娠や出産、復職などから1年以内の降格や契約打ち切りなどの不利益な取り扱いは、原則として男女雇用機会均等法などに違反すると判断することを決め公表した。
例外として認められるのは、妊娠前から能力不足について指摘がされ、本人が改善する機会があったのに改善の見込みがない場合などが挙げられている。
今回の決定のきっかけは昨年10月の最高裁判決だ。妊娠中に負担の少ない業務に移ったことをきっかけに降格させることは原則違法だとした判決だった。今回の厚生労働省の決定は既に全国の労働局へ通達が出されている。
朝日新聞によると、マタハラ被害者でつくるマタニティハラスメント対策ネットワーク(マタハラNet)が30日、被害の実態をまとめた「マタハラ白書」を公表した。インターネットで1月に調査しマタハラ被害を経験した女性186人から回答を得た。
「マタハラ白書」によると企業規模は44%が社員数100人未満であったが、一方で1000人以上が28%、東証1部上場企業も19%あった。マタハラの加害者は直属の男性上司が30%と最も多く、男性からが55%を占めたが、一方で女性から受けた人も3割に上った。
改めて、マタニティハラスメントに当てはまる事例はどんなものがあるのだろうか。マタハラNetでは下図のように4つの分類をして説明している。
図記載のURL
http://mataharanet.blogspot.jp/p/blog-page.html
大きく分けて個人的に妊娠・出産した女性が働くことを良しとしないケースと、組織的に退職に追い込もうという会社の圧力がある。個人的に自分の価値観が古くマタハラしている本人に悪意はないのであるが、結局マタハラしてしまうのが「昭和の価値観押しつけ型」、個人的に妊娠や出産で休んだ分の業務をカバーさせられた同僚等からの嫌がらせが「いじめ型」。
組織的は会社の社風や方針が問題である。妊娠や育児を理由に休んだり早く帰ったりすることを許さない職場風土がパワハラ型、一番わかりやすいのが妊婦や子持ち女性に上司が行う退職圧力のケースが「追い出し型」である。
今まで多くの女性が泣き寝入りしていたが、今回の厚生労働省の通達で妊婦や子供を抱えた女性労働者の労働環境が働きやすいものに変わることになることを期待する声は多い。
(C)wowKorea