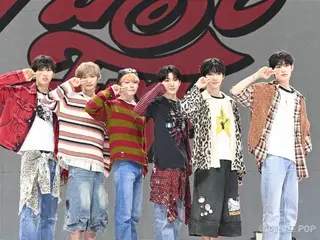ソン・ガンホ の最新ニュースまとめ
2月23日(日)に、東京・日本記者クラブにて来日記者会見が行われた。
会見冒頭、まずはアカデミー賞受賞、さらに日本での大ヒットを受けて、コメントした。
ポン・ジュノ監督:カンヌ受賞からオスカー受賞まで、非常におめでたいことでもあり、とても喜ばしいことでもあるのですが、これは私たちが最初から計画していたわけではありません。賞を目標に映画を作っていたわけではないので。受賞したことは非常に光栄なことではありますが、韓国だけでなくフランスやドイツ、アメリカ、イギリス、日本まで1年がかりで公開がずっと続いており、どの国の方も熱く反応してくださったので、それが何よりうれしく思っています。まず、北米で昨年10月に公開されたのですが、今年1月中旬のオスカーノミネートの発表がある前に、アメリカでの外国語映画トップ10に入ることができました。先に、アメリカの監督が熱い反応を示して下さった、それを受けてオスカーでもいい結果を得られたということに意味があるのではないかと思います。日本でも今年1月頭に公開されて、観客のみなさんが熱く反応してくれたことに感謝したいと思います。本当にこのような喜ばしいことになりましたことを、今回東京にまた来て、日本の観客のみなさんの関心に感謝をお伝えしたいと思っています。
ソン・ガンホ:お会いできてうれしいです。ソン・ガンホです。今回の作品において東京を訪れるのは2回目となります。とてもうれしく思っています。「パラサイト」が日本の観客のみなさんにも歓迎され、興味深い映画として受け入れられたことをうれしく思います。今から約20年前は、韓国の映画が日本でも大きく紹介されていましたが、その後は韓国と日本の映画の交流というものが少なくなってしまったように思います。韓国と日本は近い国であるにもかかわらず、一時のような活発な交流が薄まった時期がありました。しかし、今回の「パラサイト」という映画を契機にして、韓国の素晴らしい監督が作る作品が、そして日本の優れた芸術家の作品が、段々と人々の愛情を受け、関心を寄せられているのではないかと思います。お互いの国の作品に関心を持ち、お互いに声援を送り合える関係がまた戻ってきて欲しいなと思います。この『パラサイト』が日本でも好評を博したように、お互いの国の文化への共感が持てればいいなと思います。
Q.「パラサイト 半地下の家族」の何がここまで多くの観客を魅了したと思いますか?
ポン・ジュノ監督:日本だけでなくイギリス、メキシコ、韓国、フランスでもとても良い反応が出ています。北米でも記録をずっと更新している最中なのですが、正直なぜこの作品がここまで受け入れられたのか私自身もよくわからないです。この映画は、色んな国で熱い反応を得ることを目標にして作ったわけではありません。いつも通り、韓国の俳優と一緒に作って、私たちの時代の普遍的なテーマを描いただけなので、今の状況はうれしくもあるのですが、私自身とても不思議に思っています。プロモーションの過程で、様々な国を回って耳にした反応をまとめると、やはり“貧富の格差”を描いたことが同時代的なテーマだという反応が多く見受けられましたが、私は少し違うのではないかなと思います。なぜなら“貧富の格差”というのは観る人にとっては、ある意味居心地の悪い部分もあるかもしれません。なので、そういった理由ではなく、それ以上にみなさんに訴えかけた部分というのは“予測不能なストーリー展開”、特に後半のストーリー展開に熱い反応があったように感じました。カンヌ映画祭では、後半のストーリー展開に関するネタバレはしないようにとお願いをしたのですが、やはり後半のストーリー展開が新鮮だったという声が多かったように思います。さらに、俳優による魅力が大きかったのではないかと思います。俳優が表現している感情や表現、これが万国共通語としてみなさんに届いたのではないかと思います。俳優たちが醸し出す魅力が訴える力が大きかったと思います。特に、アメリカでは俳優組合賞もいただき、映画の中の10人の素晴らしいアンサンブルがアメリカをはじめ多くの国に熱く訴えかけたのではないかと思います。
Q.ポン・ジュノ監督とソン・ガンホさんは4度目のタッグとなりますが、お互いの素晴らしいところ、お互いにとってお互いがどういう存在なのか教えてください。
ポン・ジュノ監督:好きな俳優です。演技が本当に素晴らしい。この役柄を演じるのはこの方なんだと頭で思い描きながらシナリオを書いていると、心がとても穏やかになって、とても楽な気持ちになって、自信も沸いてきます。まるで草の上を走り回っている子馬のような自由な気持ちになります。
ソン・ガンホ:普通、撮影現場で監督と俳優はたくさん話すと思われると思いますが、私はあまり話はしません。私の場合、この作品を通して監督は一体何を語ろうとしているのか探っていくのが好きなんです。それは俳優として難しい過程ではありますが、同時にとても楽しい過程でもあります。ですから、現場ではあえて監督に尋ねるのではなく、自分で見つけていこうとしています。この20年間、監督と一緒にたくさんの仕事をしてきましたが、それを振り返って感じることは“祝福”でもあり“苦痛”でもあるということだと思います。“苦痛”というのは、芸術家としてポン・ジュノ監督が目指している高い野心を、私が俳優として十分に達成すべきであるという“苦痛”であります。
Q.「パラサイト 半地下の家族」を通して、監督が1番伝えたかったことは何でしょうか。
ポン・ジュノ監督:全世界で同じ状況に置かれ、同じ“苦痛”というものを抱えていると思います。それがいわゆる“二極化”という呼び方もされていますが、その“二極化”を暴きたかったという意図よりも、未来に対する恐れという感情が強かったです。私自身、息子を1人育てていますが、未来の私たちの社会がこの“二極化”を克服しうるのか、それは容易いことではないように思います。私は悲観主義者ではありませんが、今後私たちはどうしていくべきなのか、今私が抱えている不安や恐れというのは、例えクリエイターでなくても、この時代を生きているすべての人々が抱えているのではないかと思います。なので、この不安や恐れを率直に映画で描いてみたいと思いました。そのメッセージやテーマを伝えるうえで、私は普段から真顔で伝えるというよりも冗談交じりに伝えることが好きなので、この映画でも自分が伝えたいメッセージを声高に主張するのではなく、あくまでも映画的な美しさ、映画的な活力の中で、シネマティックな興奮があるなかで伝えていきたい、俳優さんたちによる豊かな感情とともに伝えたいという気持ちがありました。
Q.この映画では“匂い”というのが一つのキーワードになっていると思いますが、なぜ“匂い”にフォーカスを当てようと思ったのでしょうか。
ポン・ジュノ監督:映画は、イメージとサウンドで作られるものなので、“匂い”を表現するというのは難しいことですよね。ですが、このような優れた俳優さんの表現によって、私自身シナリオで“匂い”について思う存分書けたのではないかと思います。俳優さんたちが匂いを嗅いでいる時の表情や、自分から匂いがするのではないかという表情を見事に演じていたので、シナリオを書く段階から“匂い”に関する繊細な状況も書くことが出来ました。この“匂い”というものが、映画が伝えるストーリーに似合っているものだと思いました。この映画は“貧富の格差”ということを描く以前に、“人間に対する礼儀”が失われた時にどんなことが起きるのかという瞬間を描いた映画でもあります。“匂い”というのは、普段の生活のなかで感じたとしても話すことはなかなか難しいことですよね。やはり相手に対する礼儀に関わることですので。“匂い”というのはその人が生きている環境や、その人の労働条件、どんな状況に置かれているのかを表すものでもあると思いますが、それについて口に出すのはやはり難しいです。映画の中では、意図せず“匂い”について話を聞いてしまい、そのことによって人間に対する礼儀が崩れ落ちる瞬間、ある一線を越えてしまった瞬間を描いています。
Q.ソン・ガンホさんは“匂い”の演技をするうえで苦労した点、工夫した点はありますか?
ソン・ガンホ:「線を越えるな」という表現が、この映画の中で出てきます。この映画において“線”や“匂い”というのは目には見えないものです。この目には見えないものを映像を通して見せることはできません。こういった漠然とした観念的なものを表現する方法はないので、ドラマの構造の中に入っていって心理的に理解するということを心がけました。
Q.監督にとって日本の映画界はどのように映っていますでしょうか。
ポン・ジュノ監督:個人的に親しくさせていただいている日本の監督が多くいらっしゃいます。そして、日本は映画の長い歴史や伝統を持っているので、歴史的な優れた監督がいるというのが第一印象です。今村昌平監督や黒沢清監督、阪本順治監督、是枝裕和監督などの作品が本当に好きです。彼らとは長い間お付き合いをさせていただいています。韓国の映画産業において、国家的な支援があるのはインディペンデント映画やドキュメンタリー映画の領域に焦点が当てられているので、私やソン・ガンホさんが参加している映画は主に民間企業で出資・配給・制作をするという状況になっています。同時に、韓国の映画産業が今うまく健康的に回っているとも言えるかもしれません。日本では、主に漫画やアニメーション産業が国際的に広く知られていますが、私個人としては日本の監督や日本のフィルムメーカーが持つ多様なスペクトラム、そして幅広い映画の世界に興奮を覚えます。
Q.カンヌ国際映画祭パルムドール受賞とアカデミー作品賞受賞、それぞれ喜びの質に差はありましたか?
ポン・ジュノ監督:個人的には“衝撃”と“歓喜”が共存しているので、2つを比べるのは簡単なことではないのですが…。カンヌには、イニャリトゥ監督やケリー・ライヒャルト監督など、私が個人的に好きな監督が審査員の中にたくさんいました。ヨルゴス・ランティモス監督など、私が普段から好きだった監督がこの映画を好きになってくれたという喜びがとても大きかったです。審査員長を務めていたイニャリトゥ監督が「満場一致だった」ということをとても強調してくれて、よりうれしく思いました。アカデミーは8000人以上の方が投票しているので、それぞれのお名前やお顔は知りません。そして、私とソン・ガンホ先輩をはじめ、みんなで5か月以上に及ぶオスカーキャンペーンという長く複雑な道のりを初めて体験しました。キャンペーンの最中はとても長い時間だったので、本来シナリオを書くべき時間なのに何をやってるんだろうと思ったり、暗く感じられたり、大変だなと思ったこともあるのですが、今振り返ってみると、あのキャンペーンは、とても複合的で巨大なスケールの中で映画を検証していくというプロセスもあったように感じます。この映画のどこが優れているのか、どんな想いでみんなが参加しているのか、どのようにこの映画が作られているのか、映画に対して長い道のりの中で一つ一つ検証されていくという印象を受けました。
ソン・ガンホ:もちろんカンヌもアカデミー賞も同じようにうれしいことではありました。ただ、カンヌ国際映画祭での賞は、初めて賞をいただいたということもあり、あまりにもうれしくて、ポン・ジュノ監督の胸元を強く何度も叩いてしまいました。そのことによってヒビが入ってしまったという話を聞いて、アカデミー賞のときは胸を叩くことは避けて、首元をつかむとか背中や頬を叩くようにしました。笑えないハプニングではありますが、すごくうれしいんですが、ポン・ジュノ監督の痛いところを避けて喜ばなくてはいけないということがありました。
Q.2006年公開の「グエムル-漢江の怪物-」という作品では、ウイルスが蔓延したかのような状況で社会がパニックになった時に国家がどのように向き合うかというのがテーマになっていたと思います。そして、今まさに東アジアで同じような状況になっていますが、お2人はどのように思っていますか?
ポン・ジュノ監督:「グエムル-漢江の怪物-』」でウイルスの話は出てきますが、結局ウイルスはなかったと明かされますよね。最近の状況を見ていると、浦沢直樹さんの「20世紀少年」などが思い出されます。こういった現実と創作物が、時代の流れの中で相互に侵入し合っていくというのは自然なことなのではないかと思います。実際のウイルスや細菌が体の中に入るという恐怖以上に、人間の心理が作り出す不安や恐怖の方が大きいのではないかと思います。そういった不安や恐怖に巻き込まれすぎてしまうと、逆にそういった災害を克服するのが難しくなってしまうのではないかと思います。「グエムル-漢江の怪物-」では、実際には存在しないウイルスをめぐって人々がパニックに陥り、そこから起こる騒動が描かれていました。今は映画とは違い、実際にウイルスも存在しているわけですが、この事態にあまり恐れすぎてしまうともっと恐ろしいことが起きてしまうのではないかと思います。もうじき私たちはこの問題を懸命に乗り越えていくのではないかと、希望的に捉えています。
Q.映画を作る時に1番目標にしていること、心がけていることがあったら教えてください。
ソン・ガンホ:アメリカの俳優組合賞において、アンサンブル賞というのを「パラサイト」チームが受賞しました。その時に私が代表して受賞のコメントをしたのですが、この映画は「パラサイト」というタイトルがついていますが、内容を見てみると、私たちはこの社会をどう生きていけばいい世界になるのか、“寄生”ではなく“共生”を描いた作品になっています。その作品がアンサンブル賞を獲れたということで、私たちはちゃんとこの映画を作ることができた、ちゃんと伝わったんだと感じることが出来ました。映画を作るということは、それに快感を伴い、価値を見出すことが出来ます。この「パラサイト」という映画を観た方たちが、同じ快感や価値を味わうことができたからこそ、世界中で好意的に受け止めてもらえたのではないかと思います。おそらくポン・ジュノ監督も同じだとは思いますが、映画を作るにあたって必ずしも何か大きな意味がなければダメだとは思っていません。自分たちが映画を通して表現したいことを、いかに面白く、興味深く表現できるか、どのようにしたら観客に伝えられるかということを、俳優として常に探求し、研究しているところです。
ポン・ジュノ監督:私は映画を作るときに、実は目標があるのですが、恥ずかしくてお話しするのは憚られるのですが、告白しなきゃならない状況ですよね(笑)自分で言うのは恥ずかしいのですが、自分の作品がクラシックの映画になってほしいという妄想を持っています。クラシックになるということは、つまりその映画が時間や歳月を乗り越えていったということになります。例えば、キム・ギヨン監督の「下女」や黒澤明監督の「七人の侍」、アルフレッド・ヒッチコック監督の「めまい」のような作品が作りたいと思っていますが、これはもう妄想ですよね(笑)そうするために映画を作る時は、自分が書いているストーリーと1対1で向き合うことを心がけています。透明な状態で向き合うこと、他の何か目的を持ったり、例えば何か賞を獲りたい、どこかの国で興行的に成功して欲しいという不純物が混ざることなく、あくまでもストーリーと向き合って自分自身が対決するような透明な状態で映画を準備することを心がけています。
Q.多くのメディアが、韓国の半地下での生活について興味本位で取材していることに関してどう思いますか?
ポン・ジュノ監督:色んな国によって様々な住居形態というものがありますが、裕福な豪邸やそうでないエリアは混在していますが、半地下という住居形態はかなり独特なので、日本や他の国のメディアも関心を持たれたのではないかと思います。半地下だけでなく、映画の冒頭に登場するスーパーマーケットや、雨のシーンで出てくる階段など、多くの映画ファンの方がロケ地巡りをしているという状況が起きています。映画の人気に伴うことではありますが、実際そこに住んでいる街のみなさんには苦労をかけてしまっているので申し訳ない気持ちです。メディアの方が取材に来たり、ファンの方がロケ地巡りをしているということに関しては、その場所が深い山奥や無人島ということではなく、リアルに普通の人々が生活している場所ですので、その方たちにご不便をかけないことを最優先に配慮してほしいです。クリエイターとしては、実際にある場所に関心を持っていただけるという効果はあったわけですが、そこに住んでいるみなさんにはご不便をおかけしてしまったという点については申し訳ないと思っています。
Copyrights(C)wowkorea.jp 0