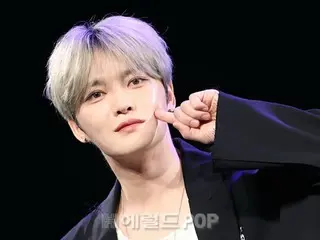キム・ジス の最新ニュースまとめ
女性は、独りで部屋にいる時は鼻をほじったり、爪も適当に切って散らかしたり、放屁もする、人間”だということである。これは、女性に対する概念が、男性の一方的な規定であることを指している。ショペンハウアーは、「女とは、男の想像の産物」だと言っている。男性が考えている女性というものは、実際とは大きく異なるということだ。女性という広い範疇に、それぞれの個性を考慮すれば、想像と違いすぎるのは当たり前である。
清楚なイメージからセクシーなイメージまで、多くの映画における女性は、男性の視点によって作られるが、イ・ユンギ監督の『女・チョンヘ』は、このような男性の想像から一歩離れているかのように見える。
映画は始めからチョンヘ(キム・ジス)の日常を一つ一つ映し出している。ガーデニングや寝起きの姿、買い物をして1人で食事する様子、洗髪・歯磨き後にドアを出て見る朝の出勤風景、職場である郵便局の生活など、退屈なほど単調に続いていく。チョンヘの顔には表情の変化さえない。美しく華麗なイメージや清楚なイメージとは程遠い。
よく男性たちが考えている女性性が現れるようなイメージは自制されている。日常は単調でありながらも雑でなく淡々としている。ある映画的な想像力が発揮されるのではなく、日常の姿が淡々と描かれる、ただそれだけだ。
だがこの映画さえも、もしかしたらある男が思い描いている想像だと言えるかもしれない。パク・ワンソが指摘した、男の考えが変わるようなシーンが現れないという点を考慮すればなおさらだ。何より、女性の心理とその因果関係が削除されており、もしかしたら『女・チョンヘ』はもう一つの、男性の想像する女性のイメージに見えるかもしれない。
男性監督が女性の視点が入った映画を作る際、女性のある種の脅迫心理が反映される微妙なシーンを考えると、なおさら男性の想像に頼るしかない。フェミニズム評価のほとんどが事実だとすると、それらを意識しないわけにも行かず、これらの評価に男性的内化を加えた脅迫観念が映画に添えられたりする。
映画『女・チョンヘ』は、時々主人公の視点と、それに向き合った対象を通じて何かを語ろうとする。この時大事なのは“女・チョンヘ”ではなく、その視点を通して映し出している対象であろう。移されるのはチョンヘという女ではないのかもしれない。
この映画の中では、女性から見た男性たちが登場する。映画はこの男性たちを通して、チョンヘの心の傷と自我を顕わにする。チョンヘは少しずつ、ラカンの言うところの『鏡』を通して彼らを映し出し、心を通わせ、克服しつつ前へ進んでいくべきだ、と観客は思うだろう。
映画は日常の風景は変化させずにチョンヘだけを中心に描いているが、ここに急に飛び込んでくる男がいる。別れた男。彼は女性側の話とその欲求をちゃんと聞かないマッチョな男性の類型だ。
新婚旅行中、ホテルで男の強引な行為に、「どうしてこんな…」とチョンヘが嫌がるシーンがある。その後で彼は「初体験の時、どうだった?」と聞く。答えたくないチョンヘは仕方なく「痛かった」とだけ答えた。痛みだけが大きくなる関係。そのためなのか、チョンヘは彼を去った。彼にとって、チョンヘの痛みは興味の対象ではない。
真にチョンヘを苦しめた最初の男は親戚の1人で、映画は彼女の幼い頃の性暴力による傷跡を露わにする。しかし、必ずしも彼女の持つ傷跡に関係するシーンは、男性の様子ばかりが登場するわけではない。靴屋の店員、彼女はチョンヘを“オンニ(お姉さんの意)”と呼びながら、絶えず自分の好みをチョンヘの望みであるかのように強要する。
「オンニと呼ばないで」
「それって変ですか?」
次の風景は、愛に対する勇気を描いたものである。
郵便局にしばしば訪れる男にチョンヘは言う。
「私の家に来ます?」
男は原稿の締め切りで数日徹夜をしたと難色を示しながらも、行くと答える。チョンヘは食料を買い込んで料理を用意するが、彼は来なかった。チョンヘはおかずを一つ二つつまんで結局ご飯まで食べてしまう。事情はどうあれ、失礼な男である。
居酒屋で、ある一行とケンカし、チョンヘのテーブルに来た男。自分の酒でもないのにチョンヘの酒をがぶがぶと飲む、うるさく騒々しい男。しかし揺れ動き、惑いながら自分を自虐する男。そして泣いているその男をやさしく包み込むチョンヘ。
彼らは一方通行で相手を配慮しない男たちだが、彼らにも心の傷があることを認め、それを憐れみ抱擁するという象徴のようにも見える。しかしその男たちの“心の傷のナイフ”がチョンヘの手に握られたのは、彼らがチョンヘの傷を一層深めたためであろう。
しかしながら、自分を犯した男に復讐せず、彼女は再び日常に戻ってくる。ナイフは極端な意思表現で、傷に対する反応だが、チョンヘはナイフで刺すことはおろか、結局は一言もまともに口にできぬまま日常に復帰する。言い換えれば、これが映画が批判している自閉性の部分である。映画で描かれている男たちは、一様に平凡に見えながらも、一方的な男性たちのタイプに近い。
チョンヘは、自我中心主義とか我が強すぎると批判されている。しかしチョンヘの視点から見た男たちが彼女に与えた傷や彼らのイメージは、チョンヘが何故自分という深淵に沈んでいるのか、という答えを見せるものだ。
表情を消し、感情を削除するということ、自分の中に居座るということは、自分ひとりだけの問題ではないだろう。分かり合えないということは、チョンヘ自身の問題である以前に、対象である男たちにも問題があるのだ。
しかし、傷を多く持つ人が、他人にも多くの傷を与えるのに比べ、チョンヘはむしろ自らその傷を、自分の中で、感情さえ無いまま耐え抜こうとする。その耐えているということさえ表さない。それが“女性であるがゆえに自分の中に押しとどめて耐える”という設定ならば、まさにこれこそ男性が思い描いている“女性の視点”の映画でしかない。
沈黙で観客とだけ通じ合うのは映画的な空間力においてのみそのように見えるだけだ。この沈黙では、現実はどうあれ、人と人、男と女の心の隔たりからは抜け出せない。映し出すだけで“鏡”を通して何かに向けて進んでいくチョンヘが存在しないという残念さはここから生まれるのだ。
Copyrightsⓒgonews & etimes Syndicate & wowkorea.jp
Copyrights(C)gonews & etimes Syndicate & wowkorea.jp 0