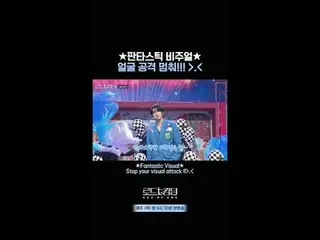その結果として24日夜に公表されたARF議長声明は、どちらかを支持するというより双方の立場の間を取った妥協の産物と評価される。韓国は全般的に、哨戒艦沈没事件を受け国連安全保障理事会が先ごろ採択した議長声明への支持を取り付けるという「成果」を上げたが、同時に事件に関する北朝鮮の責任を明記できないという「限界」も露呈したというのが大方の外交専門家らの見方だ。
声明は哨戒艦沈没事件に言及した第8項で、攻撃で引き起こされた沈没事件に「深い懸念」を表明し、「人命損失への哀悼」「安保理議長声明への支持」などを明記したが、攻撃の主体として北朝鮮を指摘することはできなかった。
ひとまず、議長声明が安保理議長声明を支持し、基調を維持した点は成果と評価できる。安保理議長声明はほぼ7対3の割合で韓国側の立場が多く反映されており、この声明への支持が明記されていること自体に意味があるというのが、政府当局者らの説明だ。
議長声明が第9項で「関連の国連安保理決議の重要性を強調する」とし、決議の完全な履行を強調したことも、評価に値する。北朝鮮への制裁を明記した安保理決議1718と1874を中心とする国際社会の制裁推進に、正当性と意味を付与し得るためだ。
また、同じ9項で北朝鮮核問題について「完全かつ検証可能な朝鮮半島非核化」と明記したことは、韓米が堅持する北朝鮮核問題への対応基調を反映したものと評価される。
あわせて、国際社会の人道的関心事への対処が重要だとした第10項は、北朝鮮の人権問題に対するメッセージと受け止められている。
しかし、文全体の構造と表現を分析すると、成果だとばかりは言い難く、むしろ政府の外交力の限界をさらけ出したとの指摘も出ている。何より、安保理議長声明の中身を明記しないまま、単に支持だけが記されたことから、北朝鮮が有利に解釈する可能性を残したと分析される。
特に、第8項で「攻撃(attack)」という表現は含まれたものの、北朝鮮を「糾弾(condemn)」するという表現は除かれ、安保理議長声明の基調から後退したと指摘される。安保理議長声明と同様に、哨戒艦沈没の責任主体を北朝鮮だと明示できず、攻撃に対しても「糾弾」ではなく「懸念」にとどまった。
こうしたことから、北朝鮮が今回の議長声明を都合よく解釈し、制裁の不当性を主張することも考えられる。ARFの北朝鮮代表団報道官を務めたリ・ドンイル外務省軍縮課長は22日、「安保理議長声明は互いに自制し、平和的に対話と交渉で朝鮮半島の懸案を解決するよう促している」とし、制裁はこうした声明の精神にも反すると重ねて主張した。
ARF議長声明がこうした絶妙な「政治的折衷」の形で出された背景には、南北と等しく距離を取ろうとするASEAN特有の中立路線があるようだ。だが、毎年ARFの舞台で朝鮮半島懸案に関して北朝鮮により明確なメッセージを送れず、政治的な妥協と折衷を繰り返している状況は、韓国のグローバル外交における大きな「欠陥」だとの批判が出ている。
特に、哨戒艦沈没事件と北朝鮮核問題は、国際社会の一致したメッセージと一糸乱れぬ対応が求められることから、今回のARFでの外交戦は大きな悔いを残したと指摘される。
今後は韓日米と中朝ロに分かれ、沈没事件の対応をめぐり鋭く対峙(たいじ)する可能性が大きく、朝鮮半島情勢に新たな「冷戦」の気流が広がる見通しだ。
ATTACK の最新ニュースまとめ
Copyright 2010(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0