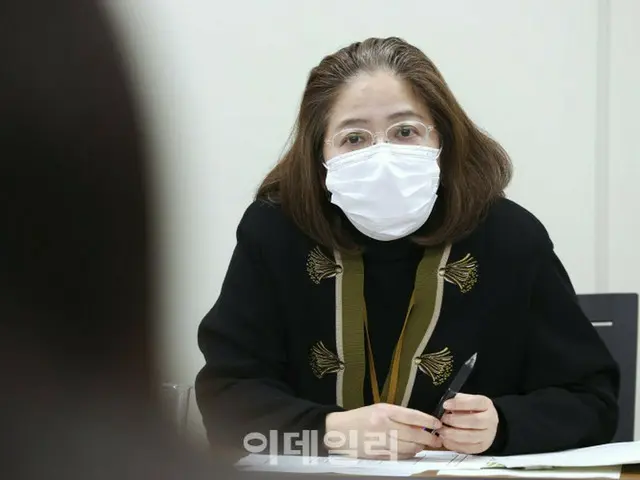19日に日本の国立社会保障・人口問題研究所で会った年金の専門家たちは、2004年の日本年金改革の主導勢力として小泉純一郎元首相を挙げた。国立社会保障・人口問題研究所の林玲子副所長は「政治を始めたばかりの彼のおかげで年金改革が可能になった」と述べた。
小泉元首相は2001年に「日本の『失われた10年』を終わらせる」という改革的キャッチフレーズを掲げて首相に当選した。自身が自民党の所属であるにもかかわらず、自民党に疲労感を感じた大衆のために自民党改革に貢献し、党内で野党の役割を担ったりもした。小泉元首相はこのような大衆的人気に支えられ、年金改革を一気に推し進めることに成功したのだ。
ドイツのシュレーダー首相とフランスのサルコジ大統領は年金改革を推進した後に政権交代した。しかし、小泉元首相の政権は年金改革後も続いた。小島克久博士も「(小泉元首相の場合)改革に対する恐れはなかった」と語り、「破格的な改革を通じて支持を得た」と回想した。
日本政府は財政安定化目標の保険料率を2004年の13.58%から毎年0.354%ずつ引き上げ、2017年には18.3%に引き上げた。その後、保険料率を最高保険料率で固定した。日本で毎月18.3%ずつ年金を支払った場合、受給者はいくらもらえるのだろうか。佐藤格博士は、40年間サラリーマンとして働いて引退したと仮定すると、厚生年金と基礎年金を合わせて月に約26万円受け取ることができると推測している。ただし、事例によって差があり、これを一般化するのは難しいという説明も付け加えた。
韓国は少子高齢化が早まり、2057年と予想されていた”積立金が枯渇する時期”がさらに早まっている。来年の国民年金財政算出を控え、改革の必要性が高まっている。佐藤博士は韓国の国民年金の保険料率が9%であるという点に注目し「保険料率が低い。まず保険料率を高めることが必要だと思う」と指摘した。
日本はスウェーデンとイタリアで導入された自動安定化装置を見本とし、2004年に人口と労働市場の変化を反映して自動的に年金額を調整するマクロ経済スライド制を導入した。また、約100年間の財政均衡期間を設定し、安定的に基金を管理している。佐藤博士は「財政点検を5年に一度ずつ行っている」と述べ、「正確には100年ではなく95年後だが、財政がその時も維持されるとのデータが出ている」と説明した。
超高齢化と少子化を同時に経験しているが、100年後の状況を予測できるだろうか。林副所長は「人口が減少しているのに対して、働き口は増えている」と述べ、「高齢者や女性などが労働人口に加わっている。非正規職にも厚生年金を適用するなどして、何とか現在の状況を克服していけるのではないかと思う」と語った。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 107