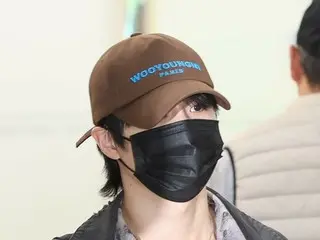ソン・ガン の最新ニュースまとめ
総制作期間7年、制作費85億ウォン(約8億5千万円)を費やした作品にふさわしく、外形的にはハリウッド映画と肩を並べる。これまでの試行錯誤を経て体得した貴重な経験が、韓国映画発展の根幹を成したと考えると、この『南極日誌』は、これをベースに韓国映画の技術力とインフラを世界市場に出し、彼らと肩を並べるきっかけを作ったという点で意味深い。『ロード・オブ・ザ・リング』のスタッフだった、ブリジット・メアリー・バークがニュージーランド・ラインのプロデューサーを、同じくラブ・ユビルがニュージーランド側のミニチュア制作を、アニメ『攻殻機動隊』の川井憲次が音楽を担当するなど、彼らが『南極日誌』に参加したことからも、この映画の地位がどんなものかがうかがい知れる。これほどであれば、“コスモポリタン”的な映画を作ろうとした監督の意図とおりの顔ぶれが揃えられたといえよう。
映画『南極日誌』は、1958年ソ連探検隊によってたった1度征服された後、誰も到達できなかったという、南極の“到達不能点”を目指す6人の探検隊員と、彼らが体験する極寒の恐怖を描いている。M・ナイト・シャマランの『シックスセンス』や『シャイン』のような得体の知れない存在に対する恐怖、スタンリー・キューブリックの『シャイニング』のような人間の内面に存在する狂気と恐怖のドラマを、この映画は南極という空間を通して見せている。「誰も成し得ない事を自分たちがやる」という劇中のセリフのように、一種の狂気じみた勝負欲と執着は、これらの映画の範疇を超える韓国的なミステリーの側面である。
マイナス80℃の極寒に、昼と夜が6ヶ月ずつ続く南極は、何人たりとも近づく事を許さない異境の地。しかし、探検隊長チェ・ドヒョン(ソン・ガンホ)とキム・ミンジェ(ユ・ジテ)を含む6人の隊員は、日が暮れる前に到達不能点に到着するという目標を持ち、世界初の無補給横断に挑戦する。イギリス探検隊の、80年前の南極日誌を発見してからというもの、順調に進んでいた彼らの前に暗雲が立ち始める。奇遇な事に、日記に登場するイギリス探検隊も、自分たちと同じ6人。日記を発見してから、彼らには不可思議な事が起こり、隊員が1人2人と消えていく。
『南極日誌』で観客が共感を感じるポイントは、仮想の極地帯で、対象のない原型的な恐怖と向き合っている、という点である。ソン・ガンホが、この映画を「『K2』や『バーティカルリミット』のような山岳映画やアクションアドベンチャー映画ではない、人間の原型的な本性を描いたドラマ」と語っているのも、この映画の主題意識を正確に突いている。新鋭のイム・ピルソン監督は映画の本質を濁さず、自分なりに自分のオーラを『南極日誌』に投影した。自然と対置した人間の姿と熾烈な葛藤、自分の内部に存在する恐怖と戦う姿を体系的に形状化したのである。しかしなんとも残念だ。視界に見えるものは雪原と吹き荒れる風、たった6人の俳優しかないという限界を克服できなかったせいであろうか。映画は緻密でないプロットや、人物間の曖昧な関係設定などが感情移入を妨げ、観客を混乱させている。まるで雪の上を歩く事だけが、この映画が示す最大の美徳であるかのように、ミステリーを増幅させただけのままラストを迎える。
観客はある面ではとても単純である。小市民的なソン・ガンホを覚えている観客ならば、慎重でカリスマ的な探検隊長チェ・ドヒョンの姿は何だかしっくりこないように感じるだろう。かつての『シュリ』でのように。
CopyrightsⓒYeongnamilbo & etimes Syndicate & wowkorea.jp
0